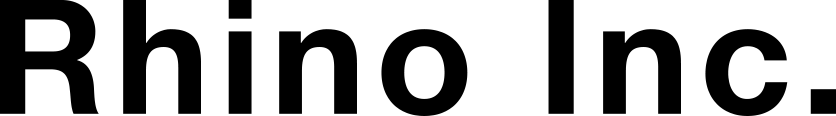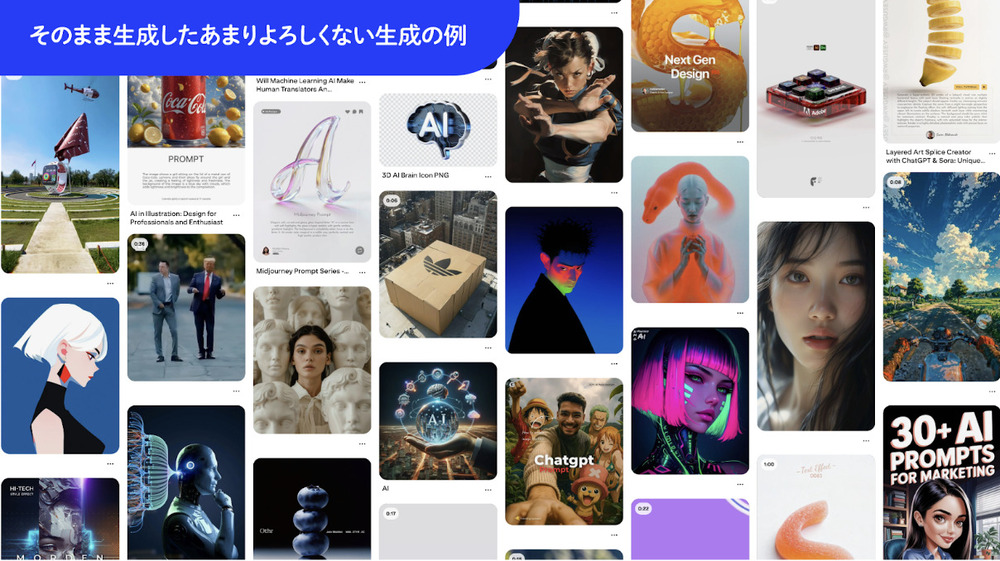役目を終えたはずなのに。

今年の1月からライノにジョインした、編集の笹です。
これまでさまざまなメディア制作に携わってきたが、自身の編集者としての原点は雑誌制作にある。見開きに40点もの写真を詰め込むモノ雑誌から、ファッション誌、高校生向けのカルチャー誌、週刊グラビア誌、ギャル誌、クラブカルチャーマガジンまで、ジャンルを問わず多くの雑誌の現場に関わってきた。
誌面構成を考え、写真と文字のバランスを取り、限られたページ数の中で最大限の熱量を表現する。その積み重ねが、編集者としての自分を形作ってきた。
しかし、雑誌の世界にどっぷり浸かっていた期間はおよそ10年ほどである。2000年代に入ると雑誌の売り上げは下降線をたどり、業界全体が低迷期に入った。その空気を現場で感じ、「これからは企業がメディアを持つ時代になるのではないか」と考え、広告媒体の仕事へと舵を切った。
ブランドや企業の思想をどう伝えるか。情報をどう編集すれば、人の心に届くのか。雑誌で培った編集力は、形を変えながらも確かに活き続けてきた。
昨年のある日、インスタグラムのフィードを眺めていると、90年代後半に自分が手がけた特集ページの写真が目に飛び込んできた。
投稿元は韓国のアカウントで、ソウルにある日本の古い雑誌を扱うカフェのものだった。その写真には多くの「いいね」がついており、素直に嬉しい反面、不思議な感覚も覚えた。日本ではすでに役目を終えたと思われていた雑誌が、国境と時間を越えて評価されていたからである。

いま、日本の古い雑誌は「ヴィンテージマガジン」として海外でも再評価されている。その背景には、昭和・平成レトロへの憧れ、高いクリエイティビティ、そして紙が持つアナログな質感と希少性がある。単なる情報媒体ではなく、視覚表現や編集思想そのものが新鮮に映っているのだ。
ファッション誌は過去のスタイルを知る資料として重宝され、「マグニフ」に代表される神保町の古書店は訪日観光客にとっての目的地となり、古い雑誌がアートやデザインの参考資料として扱われる光景も、もはや珍しくない。
アニメや音楽をはじめ、日本のカルチャーは海外からの評価によって、その価値が再認識されることが多い。雑誌もまた、その一例である。ヴィンテージマガジンとして再評価されているという事実は、編集という行為そのものが、時間を越えて価値を持ち得ることを示している。
国内にはまだ、こうした良質な「資源」が数多く埋もれているはずである。その魅力にいち早く気づき、編集し、適切な形で発信していくこと。それこそが、これからのメディアに求められる役割のひとつともいえるのではないだろうか。
ライノの一員として、その問いと向き合いながら、編集の力で新たな価値を形にしていきたいと考えている。

制作部